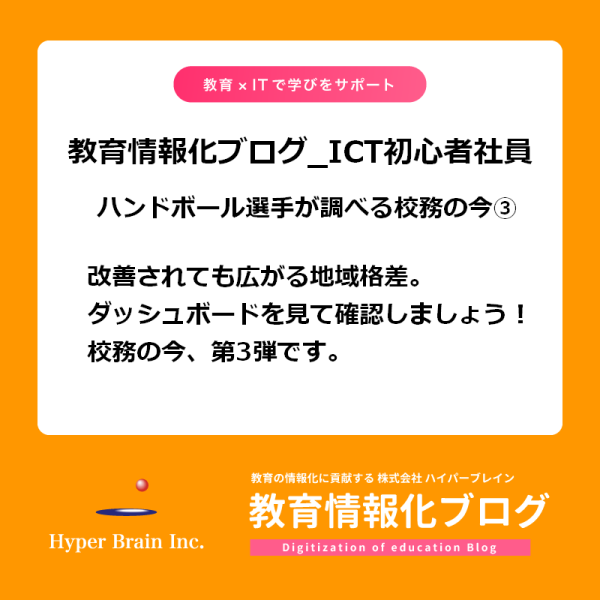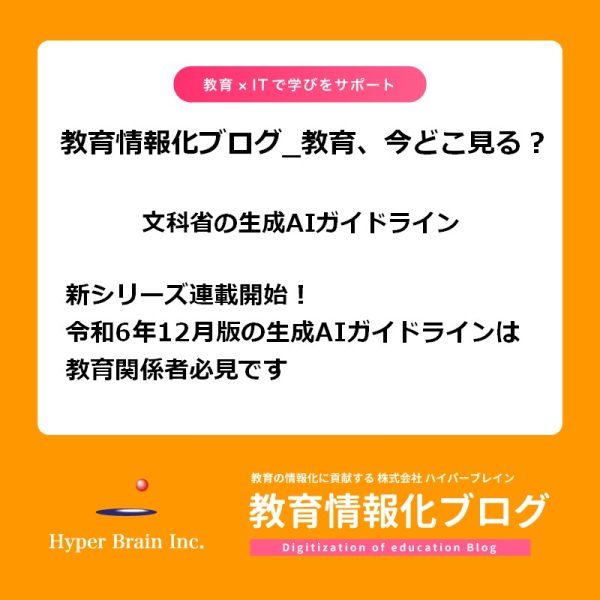教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和6年1月)42
皆さんこんにちは。
2024年1月(令和6年1月)教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン改訂版が公開されました。
平成29年10月に第1版が公開されて以降、時代の要請にあわせて何度か改訂が行われてきました。令和4年3月以来約2年ぶりの改訂です。セキュリティ、と聞くと身構えてしまいがちですが、今後の世界を生き抜くためにはどうしても必要な知識となります。過剰に恐れることなく、甘くみて大変なことになることもなく、ちょうどよい塩梅をご自分で見つけられるよう、まずはガイドラインに触れていただきたいと思います。
つい先ごろ、更なる改訂版が公開されました。ガイドラインは常に最新版をご確認いただく必要があります。
今回で先のガイドラインの解説については終了です。
第3編 付録
用語定義
教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月)の公開に伴い、令和6年1月版は文科省のリンクから直接飛べなくなりました。
よって、これを引っ張り出して解説する、というより、どうして用語定義が必要なのか、というお話をしたいと思います。
掲載されている用語の中で、難しいと感じるものは、用語定義があるととても便利です。索引代わりに使えます。これは、大体の人に通じる感覚ではないかと思います。
では、端末に関する以下の用語についてどう感じられますか?
- 校務用端末
- 校務外部接続用端末
- 学習者用端末
- 指導者用端末
自治体によっては、「校務に使う端末と授業に使う端末は1台で切り替えてる。だからそれを○○端末と呼んでいる」というようなことがあるでしょう。このHBI通信でも何度も取り上げていますが、職員室LANと校内LANと校務系LANが同じネットワークをさすことがあるのです。
自分の持っている印象で「校務外部接続用端末」をイメージしてガイドラインを読むと、もしかするとところどころ「?」と思う部分が出てくるかもしれません。「校務外部接続用端末って何だ。うちは校務端末で全部できる」と考えて、校務端末のところだけ読むと、指導者用端末で留意しなければならないことを読み飛ばす可能性があります。
同じ言葉を使っていても、そこからイメージするものが違えば、せっかくのガイドラインも十分に活かせません。とはいえ、関係者全員の意識を統一する、ということはとても難しいので、巻末に用語集を掲載し、「このガイドラインではこういう意味で使っています」ということを書く必要があるということなのです。
こういう意図がある、ということを知ってガイドラインを活用すると、よりご自分の自治体に合った形での活用ができると思います。
長い間お付き合いいただきありがとうございました。次週からは、新たな資料をご一緒に読み解いていきたいと思います。
投稿者プロフィール

-
株式会社ハイパーブレインの取締役教育DX推進部長 広報室長です。
教育情報化コーディネータ1級
愛知教育大学非常勤講師です。専門はICT支援員の研究です。
最新の投稿
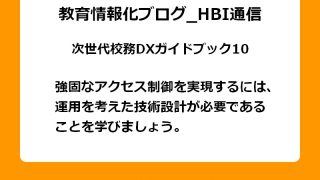 HBI通信2025年6月30日次世代校務DXガイドブック10
HBI通信2025年6月30日次世代校務DXガイドブック10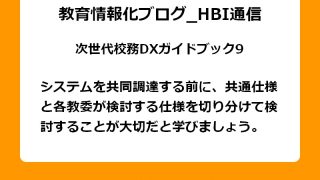 HBI通信2025年6月23日次世代校務DXガイドブック9
HBI通信2025年6月23日次世代校務DXガイドブック9 HBI通信2025年6月16日次世代校務DXガイドブック8
HBI通信2025年6月16日次世代校務DXガイドブック8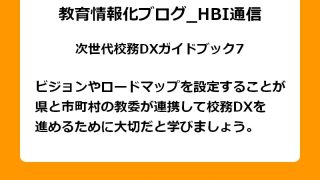 HBI通信2025年6月9日次世代校務DXガイドブック7
HBI通信2025年6月9日次世代校務DXガイドブック7