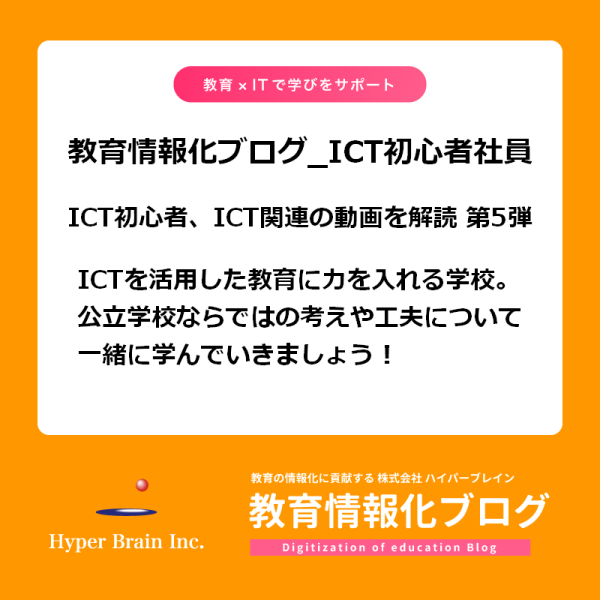次世代校務DXガイドブック13
皆さんこんにちは。
2025年3月(令和7年3月)に 次世代校務DXガイドブック-都道府県域内全体で取組を進めるために- が公開されました。
サブタイトルにある通り、「都道府県域内全体」での取組が重要である、という認識のもと「学校、首長部局、関連事業者等の幅広い関係者との共通認識を図る」ために使える資料です。行政職の皆様におかれましては、「どうして話が通じないんだ」と困られることもあるでしょう。それを手助けしてくれる資料となりますので、ご一緒に確認していきましょう。
2.次世代校務 DX を実現するために必要な取組
2-2.環境整備を伴う校務 DX の実施
(3)次世代校務 DX 環境の整備
次世代校務 DX 環境の仕様検討
(エ)データの可視化・利活用を行うための機能の整備
冒頭には「経験や勘だけに頼らず、客観的な情報を参照しながら教育活動を改善していくことが必要」とあります。経験や勘がとても大切なことは間違いないのですが、例えば若手教員に「どうしてそんな授業ができるんですか?」と聞かれて「経験してくると勘所がわかるんだよ」という回答では、ちょっと若手教員が困ってしまいますね。
そのようなことがあるのは間違いなくそうなのですが、すべてを勘と経験に頼っていては、見落としてしまう子どもたちが存在するかもしれません。そのために、データをしっかり活用し、「本質的な教育の質向上」のために「科学的根拠を求めていくことも重要」というわけなのです。
以前、いじめに関するアンケートをフォームで取ることについて、「子どもたちが紙に鉛筆で何かを書き、迷って消し、また書いて消し……という見えない心の叫びをくみ取るのが教員の仕事だ」と猛反対された先生がいらっしゃったとお聞きしました。その紙の跡から子どもたちの心の動きを読み取れる先生は本当にすごいと思います。それを否定したいわけでは全くありません。ただ、それを年に何回取ることができるのか、毎回毎回アンケート用紙を隅々まで確認してご対応される時間はあるのか、という観点でもお話をお聞きいただければと思います。フォームでアンケートを取ると、集計まで自動でやってくれますので、先生の負担は紙に比べて低いと考えられます。ということは、紙で1回取っていたアンケートを、複数回取ることができるようになる、ということです。
また、そこにはデータがあり、推移を確認することができます。その推移から先生方はお気づきになることもあるのではないでしょうか。
「教育現場におけるデータの可視化や利活用を進めることは大変重要」とある通り、データを取っても活用できない形も多かったこれまでとは違い、統計・分析できるデータを取り扱い、今まで見えていなかったものがより見える状態で、子どもたちと向き合っていただければ、先生方の強みをより活かしていただけると思います。
ただ、「データ可視化ツールはあくまで目的達成のための手段」ですので、ダッシュボードのような可視化ツールを入れることが目的ではなく、どのような子どもたちを育んでいくか、それぞれの自治体の目的に合った使い方を意識する必要があります。
実際に活用が進んでいる渋谷区では「1つのデータや情報だけでなく、本人からの生の声を含む複数の情報を掛け合わせることで、より客観的な子ども理解につながる」という声が上がっているということでした。データをダッシュボード化することで、担任だけではなくチーム学校で子どもたちを見守ることができている、というのはとても良いことです。
教育の全てをデータで語ることはまだできませんが、データで語ることのできる部分は、データを活用することで、今までになかった発想や方法、見つけられなかったことを見つけることができるようになる、など多くの利点が考えられます。
便利なツールは取り入れて、先生方には子どもたちをあらゆる角度、方面から見守っていただけるように、ハイパーブレインも全力でご支援を続けてまいります。
来週はこの続きを読んでいきます。
投稿者プロフィール

-
株式会社ハイパーブレインの取締役教育DX推進部長 広報室長です。
教育情報化コーディネータ1級
愛知教育大学非常勤講師です。専門はICT支援員の研究です。
最新の投稿
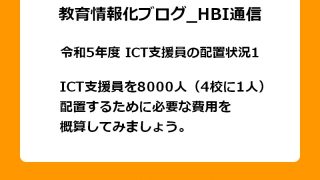 HBI通信2025年8月25日令和5年度 ICT支援員(情報通信技術支援員)の配置状況1
HBI通信2025年8月25日令和5年度 ICT支援員(情報通信技術支援員)の配置状況1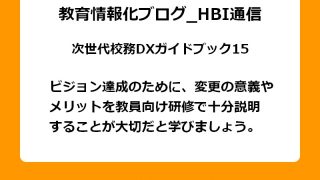 HBI通信2025年8月18日次世代校務DXガイドブック15
HBI通信2025年8月18日次世代校務DXガイドブック15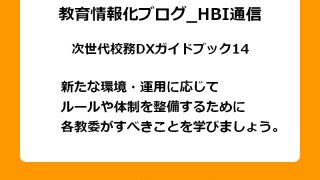 HBI通信2025年8月4日次世代校務DXガイドブック14
HBI通信2025年8月4日次世代校務DXガイドブック14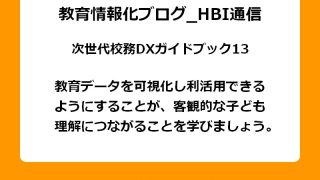 HBI通信2025年7月28日次世代校務DXガイドブック13
HBI通信2025年7月28日次世代校務DXガイドブック13