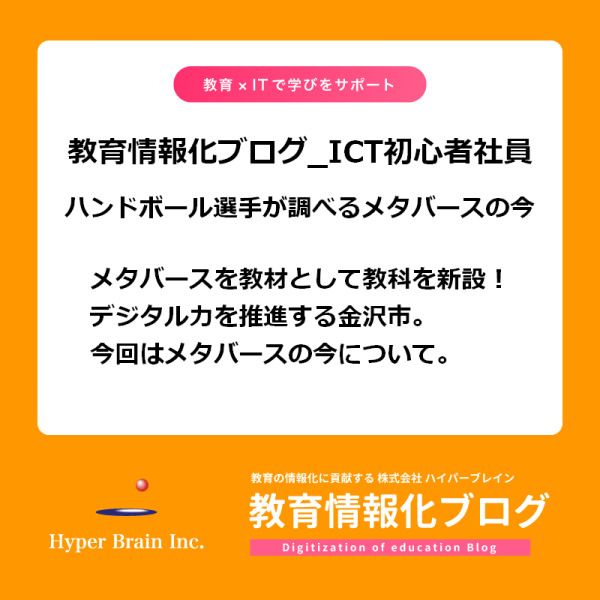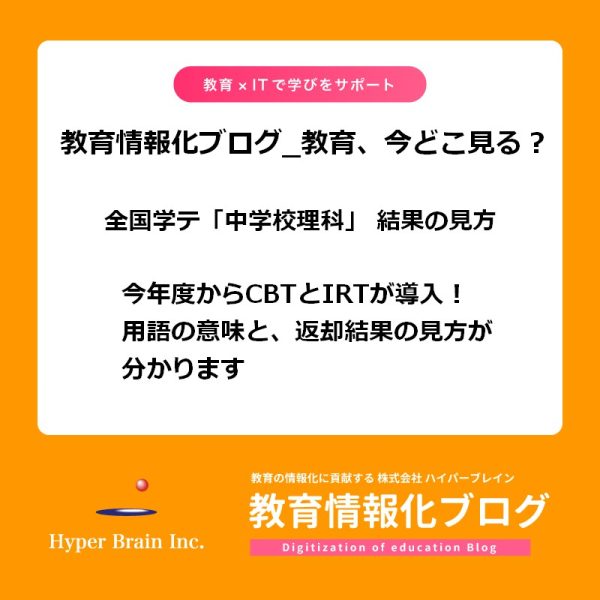次世代校務DXガイドブック12
皆さんこんにちは。
2025年3月(令和7年3月)に 次世代校務DXガイドブック-都道府県域内全体で取組を進めるために- が公開されました。
サブタイトルにある通り、「都道府県域内全体」での取組が重要である、という認識のもと「学校、首長部局、関連事業者等の幅広い関係者との共通認識を図る」ために使える資料です。行政職の皆様におかれましては、「どうして話が通じないんだ」と困られることもあるでしょう。それを手助けしてくれる資料となりますので、ご一緒に確認していきましょう。
2.次世代校務 DX を実現するために必要な取組
2-2.環境整備を伴う校務 DX の実施
(3)次世代校務 DX 環境の整備
次世代校務 DX 環境の仕様検討
(ウ)クラウド型校務支援システムの整備
これまで長い間校務支援システムは「学校にいなければ(更に細かく言うと学校の教職員のみが使えるネットワークに接続できなければ)使えない」ことが常識でした。
ところが、校務の負担を減らすには、現場がどう工夫しても現在の環境では無理、ということで、クラウドを前提とした校務の実現が求められています。そのためには、校務支援システムもクラウド環境で動くことが前提となっています。
更に、「汎用クラウドツールで担うことのできる業務は積極的に汎用クラウドツールで実施し、校務支援システムと柔軟に連携することを前提」しましょう、とガイドブックは述べています。そのうえで、県域で共同調達することが望ましく、カスタマイズは最小限、というところまで踏み込まれています。とても素晴らしいことだと思います。
学校独自の○○について、形を変えずに残していかなければならないものと、形を変えて残していきたいもの、当時は必要だったけれど今は必要ではないものなどがあると思います。その棚卸を実施して、「本当にこの校務支援システムに対してカスタマイズを実施する必要はあるのか」ということを考える必要がありますね。ある学校では「伝統ある通知票」を校務支援システムでカスタマイズしたい、という意見が大きかったところ、校長が変わったとたん「カスタマイズは必要ない」に職員の意見が変わった、ということも聞きます。「変わる」となると人間の感情として「いやだ」が出てくるのですが、議論を通して腹に落としていく必要があります。
また、外字の問題についても触れられています。
「地方公共団体の基幹業務システム(戸籍、住記、地方税など)は、文字要件(MJ+の活用等)に準拠することが法的義務となっています」とあります。引用されている 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000040 に基づいて、デジタル庁が 地方公共団体情報システムにおける文字の標準化 https://www.digital.go.jp/policies/local_governments/character-specification を実施しています。それに基づいて、文字情報技術促進協議会が文字フォントと文字情報一覧表を無償で提供しているということです。https://moji.or.jp/mojikiban/font/
校務支援システムは基幹業務システムではありませんが、基本的に戸籍情報と子どもの情報は一致するはずなので、外字についてはMJ+の活用が進むといろいろ便利になると思います。
現場の事例として、香川県と奈良県の取り組みが紹介されていました。私が特に印象に残ったのは、奈良県の
「奈良県域で行われる次の校務支援システムの更改タイミングでは、教職員間の通常時のコミュニケーションは汎用的なチャットツール等を活用することを想定し、クラウド型校務支援システムに具備されるグループウェア機能を調達の要件から外し、機能が入っている場合には OFF にできる機能を持つことを条件にするなど、システムの運用に重複がないように、十分な検討を行っています。」
というところです。重複する機能が入っていると「これはどっちで使うのだろう」と個人が使いやすい方を選んでしまい、情報が分散して仕事の手間が増えます。
重複をなくして、スムーズにいく方法を我々もご支援していきます。
来週はこの続きを読んでいきます。
投稿者プロフィール

-
株式会社ハイパーブレインの取締役教育DX推進部長 広報室長です。
教育情報化コーディネータ1級
愛知教育大学非常勤講師です。専門はICT支援員の研究です。
最新の投稿
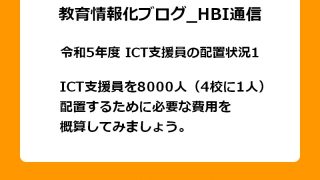 HBI通信2025年8月25日令和5年度 ICT支援員(情報通信技術支援員)の配置状況1
HBI通信2025年8月25日令和5年度 ICT支援員(情報通信技術支援員)の配置状況1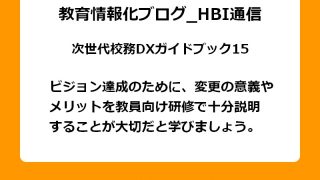 HBI通信2025年8月18日次世代校務DXガイドブック15
HBI通信2025年8月18日次世代校務DXガイドブック15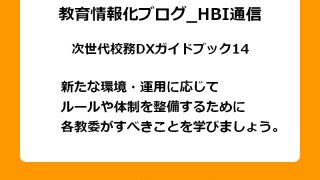 HBI通信2025年8月4日次世代校務DXガイドブック14
HBI通信2025年8月4日次世代校務DXガイドブック14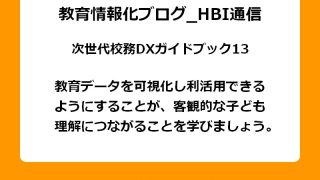 HBI通信2025年7月28日次世代校務DXガイドブック13
HBI通信2025年7月28日次世代校務DXガイドブック13