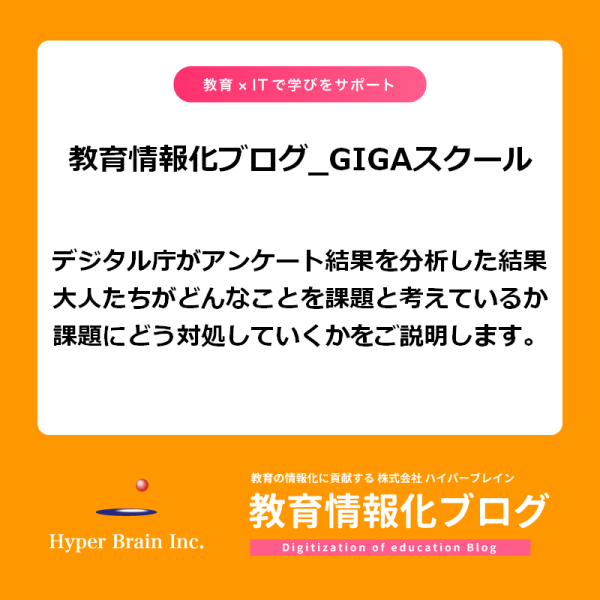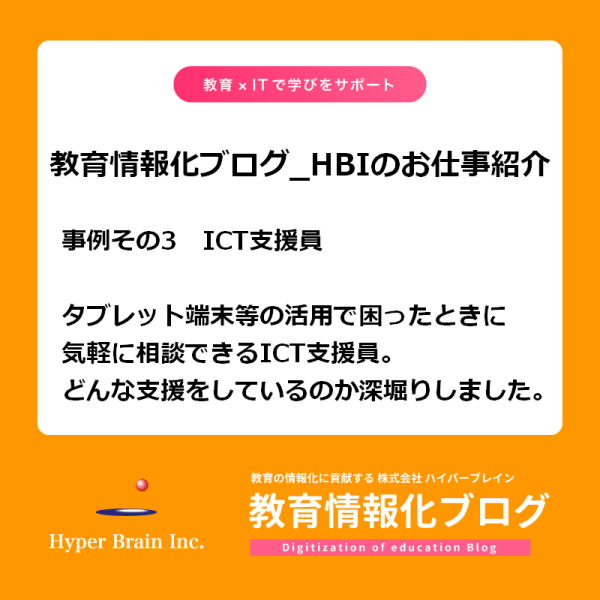ICT支援員が使えるアドラー心理学入門
私深見は「クラス会議」というアドラー心理学がベースとなった話し合いの手法を長らく教室の中で実践してきました。これを用いることで、対等感が育まれ、自己受容や他者貢献感が高まります。これらの力は、学びや人間関係を構築する上で、ベースとなる力になります。
ICT支援員がすぐにクラス会議を実践するのは難しいですが、アドラー心理学の考え方を用いて先生のサポートをすることで、子どもにも先生にも支援員にもプラスになります。まずは考え方を知っていただき、授業支援に役立てていただければと考えました。
原因論ではなく目的論
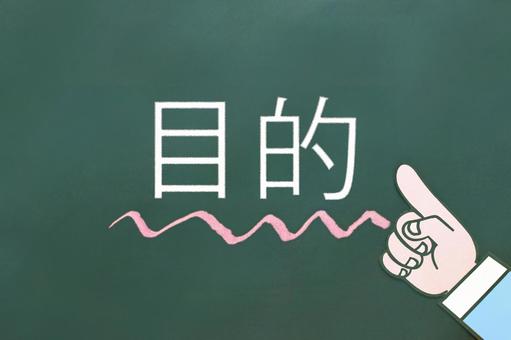
授業中タブレットを全く操作しない子がいたとします。
やり方がわからないからかな?
指示が伝わらなかったからかな?
などと考えると思います。もちろん原因を追求するのは大切ですし、それによって解決をする場合も多くあります。
けれども思いつく原因を全て取り除いても、その子が動き出さない場合があります。そんな時に心の片隅に置いておいてほしい考えが目的論です。
タブレットの操作をしないことで、この子が手に入れているものに注目をするのです。例えば、操作をしないことで、担任の先生や周りの友だちからの注目を集めることができています。サクサク進めることでプラスの注目を集めることができる子もいれば、この子のように何もしないことでマイナスの注目を集めようとする場合もあります。
みんなから注目してほしい、けれどもタブレットの操作は得意じゃないからあえてやらないことで注目を集めようとするのです。
他にも、大人との関わりを得ることができています。担任の先生が特別に声をかけてくれたり、支援員の方がずっと自分のそばにいてくれることで、他の子にはない特別な関わりを手に入れているのです。
つまり、操作がわからないとか指示が伝わっていないという原因論的な考え方と同時に、操作をしないことで手に入れているものはなんだといった目的論的な考え方が有効な場合もあるのです。
後者の場合は、授業後に担任と相談の上、その子の得意なことで注目を集める機会を作ってもらいます。例えば、鉄道好きな場合は好きな列車ベスト3を発表してもらったり、虫に詳しい場合は面白い生態をみんなに教えてもらったりします。
タブレットを操作しない子の解決方法が、その子の好きな虫の生態を発表する。そんな思いもよらないことで解決する場合は意外に多いのです。
こればかりはその子の表情や様子を細かく観察し、原因論なのか目的論なのか、もしくはどちらも入り組んだ複雑な理由なのかを見極める必要があります。
大切なのはその子が、授業に参加してよかったと思えること。そのためにどんなサポートが出来るのか考えてみるとヒントが見つかるかもしれません。
なんでなんだろうという原因探しももちろん大切ですが、時になんのためにという目的探しが有効な場合があります。特に、関わってほしいというニーズの場合は、担任一人ではなかなか手が回らないこともあるので、支援員と担任がタッグを組んでサポートする必要があるかもしれません。
けれども関わりすぎてしまうと、タブレットを操作しないと担任や支援員は関わってくれるという誤学習(誤った認識をもってしまうこと)をしてしまう場合もあるので、そこは担任と相談しながらバランスを見つけられるといいです。
支援員だけ、先生だけでは子どもの成長を支えるのは時に困難を生み出します。学校全体でサポートできるような環境を行政職の皆さんは作っていただけると、子どもも先生も支援員も幸せな学びの場が形成されていくことでしょう。
投稿者プロフィール
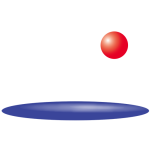
-
株式会社ハイパーブレインです。
教育の情報化に貢献し,豊かな会社と社会を作ります。
最新の投稿
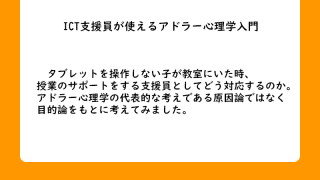 たいち先生のワンポイントアドバイス2022年6月29日ICT支援員が使えるアドラー心理学入門
たいち先生のワンポイントアドバイス2022年6月29日ICT支援員が使えるアドラー心理学入門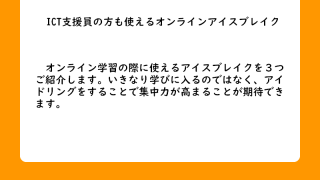 たいち先生のワンポイントアドバイス2022年6月14日ICT支援員も使えるオンラインアイスブレイク
たいち先生のワンポイントアドバイス2022年6月14日ICT支援員も使えるオンラインアイスブレイク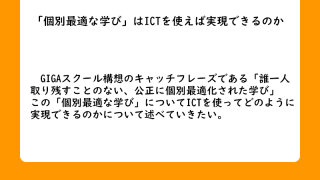 たいち先生のワンポイントアドバイス2022年5月31日「個別最適な学び」はICTを使えば実現できるのか
たいち先生のワンポイントアドバイス2022年5月31日「個別最適な学び」はICTを使えば実現できるのか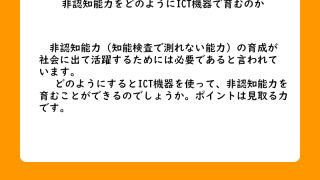 たいち先生のワンポイントアドバイス2022年5月25日非認知能力をどのようにICT機器で育むのか
たいち先生のワンポイントアドバイス2022年5月25日非認知能力をどのようにICT機器で育むのか